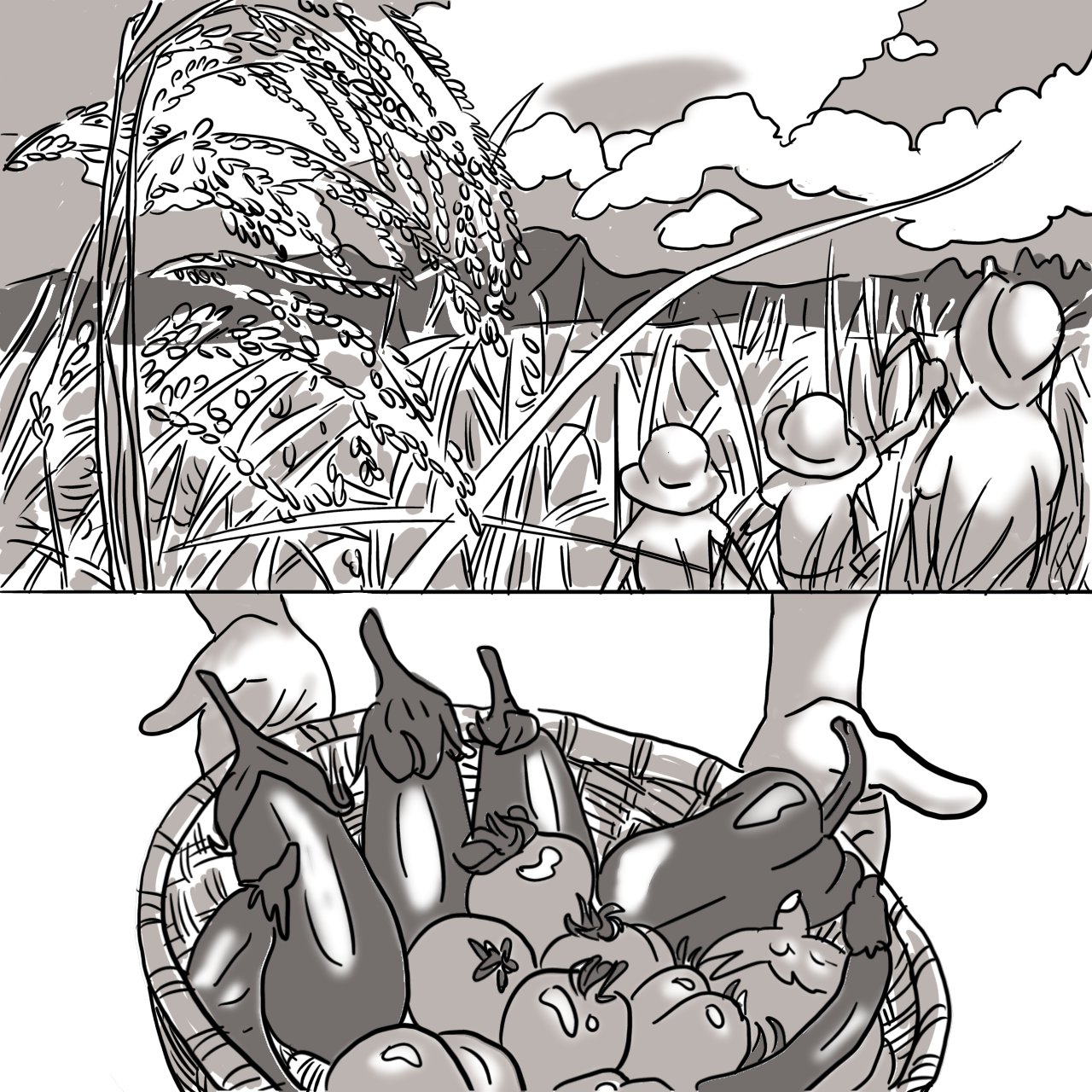パネリスト
◆萩原さとみ:「ファーム・インさぎ山」代表
◆三国清三:ソシエテミクニ代表取締役/オテル・ドゥ・ミクニ・
オーナーシェフ
◆大村直己:食育コーディネーター
◆加藤秀樹:構想日本代表
————
現代の子供をとりまく食の環境をどうしていくべきか、
食育には何が大事か、その道のプロに語っていただきました。(
以下フォーラム内容を一部抜粋、敬称略。肩書は当時のもの。)
日本は世界で最も豊かな食生活をしているにも関わらず、子供たちの心や体が蝕まれ、生活習慣病が若年化、医療費が膨らみ、食料自給率は先進諸国の中でもダントツに低い。この中で食をどう考え、ギアチェンジしていったら良いか。(大村)
本職の傍ら、全国で小学3・6年生向けに味覚の授業を行っている。6年は地方の小学校で1年間、田植え、稲刈り、精米して自ら作った米を炊いて食べる・家族や先生にも食べてもらう体験をさせる。子供たちは、大人に「お米を粗末にするな」と言われずとも一粒残さず大事に食べる。自分の土地、ふるさとに誇りをもってもらう。今の子供はやってもらうことが当然、自分から人に何かしてあげることが減った。してあげることの喜び、奉仕の心を6年の授業で実際に落とし込む。(三国)
欧州のグリーンツーリズムをヒントに、
9年前から自宅を開放し子供に生活科の実地体験(農業体験、
堆肥作り、かまどでの炊飯、味噌づくりなど)をしている。
都心から約30kmだが、周りには炭焼き体験や、
わら細工などの知恵や技術が残っており、
これらを伝えていくことこそ役目だと思っている。
現代人は木に生ったものを直接手でとって食べた経験がない。トマト嫌いの子が真っ赤に熟したのを収穫し美味しいという。自分で育ててこそ一番安心して食べられて、本物の味だということをわかってほしい。(萩原)
子供の好き嫌いが多くなった理由は、農業と消費者がかけ離れたため。昔は八百屋さんが「今これが旬だよ」と言ったことで、農家の情報がよく伝わった。流通経路が変わり、新鮮なものを食べる機会が失われた。昔は田舎の祖父母の所に行けば、採れたてが食べられた。(萩原)
日本の食料自給率は40%を切る一方で、日本人の残食分で世界の飢餓の子供を救える矛盾がある。まず日本人は旬を壊した。マグロやエビを1年中、世界中で獲って全部食べている。本来、旬というのは安全・安心を保証する。地産池消という言葉どおり、作り手と消費者はお互いを分かっているため悪いことができない。外国にいけば誰が食べるかわからず、そこまで責任をもって作らない。安全・安心は保証されない。(三国)
天然と養殖の鯛を食べ比べると、8割は養殖の方が美味しいという。とにかく肉が柔らかくて脂が乗っている。囲って運動させず、ギトギトの油を餌にまくため脂がのり、色粉を入れてピンクの鯛にする。一方、天然は餌がなく動き回るためガラガラに痩せている。岩にぶつかり骨はぼこぼこ、コブになる。色も汚く肉も硬いが天然の味、噛み締めてはじめて味がわかる。我々には歯があり、硬いものを噛み締めると唾液が出て消化を助ける。咀嚼は脳を刺激する。だからこそ味蕾が4万個になる小学3年から6年までに、甘い、すっぱい、しょっぱい、苦い味を大人が教える必要がある。(三国)
一番の問題は、戦後核家族化して、子供に箸の持ち方から教える人がいなくなったこと。味覚は体験。大人になり美味しいかまずいかを決める基準は、おふくろの味。お母さんが愛情をこめて作ってくれたものは、握り飯だろうが、おしんこだろうが、その味がその子の一生を支配する。いかに体験と記憶が大切か。(三国)
調理するだけが食育ではない。食育の本質は体験に尽きる。今まですごく自信のなかった子が、木登りができるようになり成績も上がったというのも、農業の多面的機能といわれる。農業の持つ力はすごく大きい。生きる力というのは、体験の集積からくる。(萩原)
体験を伝えることは、机上で何かを教えるのとは違い、手間暇がかかる。母親と一緒に食べものを作って食べ、一緒に片付ける食の体験から育まれることが大きい。また食育という言葉は明治からある言葉で、当時は知育、徳育、食育、体育とあり、食育がすべての子育ての基本だという考え方。私も食育の定義は色んな考え方があって良いと思う。(大村)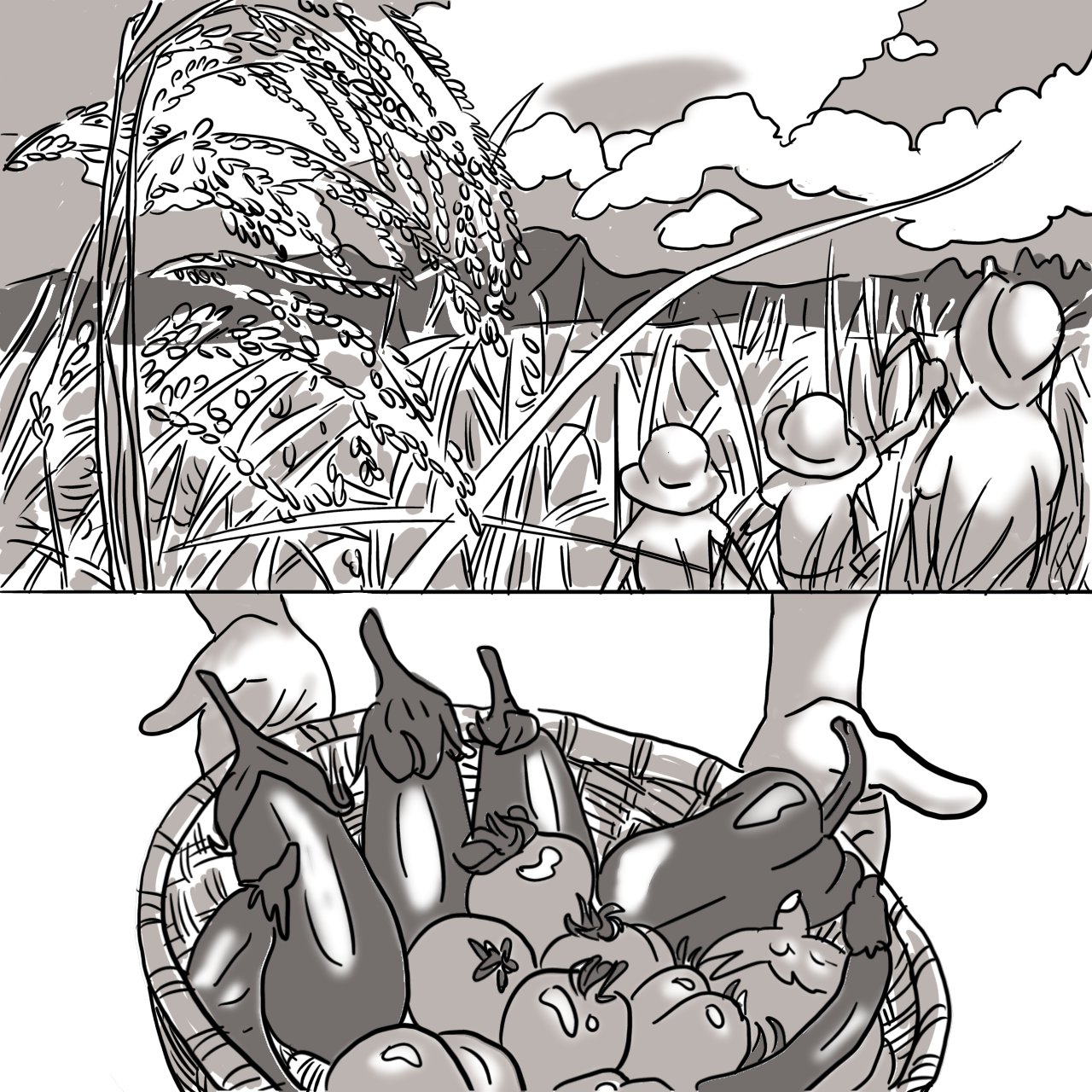
<JIフォーラムレポート10選>
これまでに行われた講演・討論の中から、今でも参考になる内容の回を選び出し、その要点をまとめたレポート。
こちらからお読みいただけます。